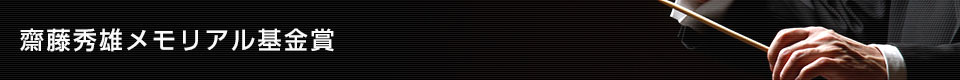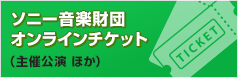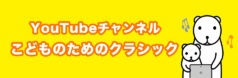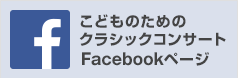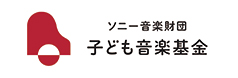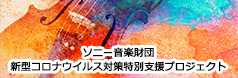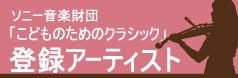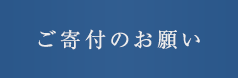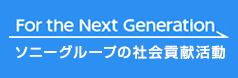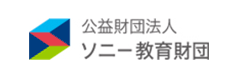第23回 齋藤秀雄メモリアル基金賞

公益財団法人ソニー音楽財団は、第23回(2024年度) 齋藤秀雄メモリアル基金賞 チェロ部門受賞者を 北村 陽(きたむら・よう)氏(20)、指揮部門受賞者を太田 弦(おおた・げん)氏(31)に決定いたしました。今回の受賞者はチェロ部門、指揮部門ともに歴代最年少受賞となります。贈賞式はライブ配信もあわせてとりおこないました。
- 受賞者
-
北村 陽(チェロ)
太田 弦(指揮) - 永世名誉顧問
- 小澤征爾 氏(指揮者・故人)
- 選考委員
<選考委員長>
水野道訓(ソニー音楽財団理事長)<永久選考委員>
堤 剛 氏(チェリスト)<任期制選考委員>
柴田克彦 氏(音楽評論家)
沼尻竜典 氏(指揮者)
吉田純子 氏(朝日新聞 編集委員)- 賞
●楯
●賞金 当該年毎に1人500万円(総額1,000万円)
贈賞の言葉
-

北村 陽 氏へ「贈賞にあたり」
永久選考委員 堤 剛【贈賞の言葉】
よく「5歳で神童、10歳で天才、でも20歳過ぎれば普通の人」と言われますが、北村君は見事にそれが正しくないことを証明して呉れました。関西で催された「泉の森コンクール」で金賞を受賞した時に名教授であられる山崎伸子の目に留まり、それ以後先生から全く妥協の無い、厳しい指導を受けることになりました。13歳の時にカザフスタンで行われた若い音楽家のためのチャイコフスキー国際コンクールで見事優勝されました。私は「大器」と呼ばれるのはこのような奏者の事を言うのではないかと思います。でもチェロの演奏だけでなく人間としても悠揚迫らない大きなものを感じさせます。音楽的な才能に恵まれ、その上体格的にもチェリストとして真に相応しいのですが、私が北村君で感服するのは彼の絶え間ない努力、研究心、独創力です。それを反映してか彼の演奏が音楽的な面で国際的に通じる幅広さとなっています。
私が驚いたのは初めての国際コンクールとして挑戦したアルメニアでのハチャトリアンコンクールで見事2位に入賞しただけでなく、ハチャトリアンの作品演奏に対して特別賞を受け、「貴方はアルメニア人演奏家と呼ばれても不思議はない!」っと褒められたのです。それはその後で受けたルーマニアでのエネスクコンクールでも同じことが起こりました。日本音楽コンクール、ブラームスコンクール、エネスクコンクール、カザルス記念コンクールとすべて1位の栄誉に輝きましたが、それは特にテクニックが優れているとか音量が豊かなどというのではなく、演奏家/芸術家としての大きな力量があっての事だと思います。勿論テクニック的にチェロの全レパートリーをこなせるだけのものを持っており、しかも彼の暗譜力は頭抜けていますが、北村君の凄さはそれらが全て一体となって音楽作りに貢献していることでしょう。
現在ドイツのベルリンに留学し、芸術大学で名伯楽のマインツ教授に師事されていますが、マインツ先生もすぐに彼の才能、熱心さ、献身的な努力、研究心を見抜かれ、素晴らしい教育をされるだけでなく力強いサポーターになられました。それに加えて数々のコンクールで優勝したことによりヨーロッパ各地での演奏の機会が増えましたが、それをバネにしてますます大きく成長されるのではないかと期待しています。最近は国内での評価も非常に高く、様々な賞を独り占めしておられる位です。「齋藤秀雄メモリアル基金賞」の選考委員のお一人である吉田純子氏に言わせると、「弾きだした最初の音から聴き手を彼の世界に引き入れてしまう」と仰っておられましたが、私もその通りだと思います。大器!頑張って欲しいと思います。
【贈賞式でのスピーチ】
北村さん本当におめでとうございます。逸材という言葉がございますけれど、北村陽さんは逸材という言葉が一番ふさわしいんじゃないかと思っております。本当に最近の成長ぶりを見るや素晴らしい。本当に果てしなく伸びていかれるのではないかと思っております。それに日本音楽コンクール以来あらゆる賞を獲得していらっしゃいまして、ひょっとするとこれは独占禁止法に抵触するのではないか!?と思われるくらい素晴らしいご活躍であると思っております。実は私がひとつびっくりしたことがありまして、それはある時北村さんがレッスンに来られた時に爪が剝がれたのです。しかも左手の爪だったんですね。これは本当に痛いですし、下手をすると致命的なことです。恐らくその時、北村さんは何かのコンクールのテープを作るために猛練習されたからだったかと思うのですけれども、その時私は自身の経験から「あぁ、これは今回テープを作るのは無理だ」と思いました。すると3日か4日後に「もう(テープが)できました!」と仰り「えぇ、本当?」と。しかも一週間ほどで治ってしまったそうです。その時、私は昔ロストロポーヴィチ先生が仰ったことを思い出しました。それは「私は自分をこんなに柔らかい身体に産んでくれた母親にいつも感謝してる」という言葉です。
器楽で音楽を続けていくには音楽的な才能が必要ですけれども、それ以外に肉体的に恵まれているというのもすごく大事だな、と感じました。ということで北村さんはやはりチェリストになるために生まれてきたんじゃないか、と本当に深く思います。
齋藤秀雄メモリアル基金賞の受賞おめでとうございました。そしてこれからも、これを機にもっともっと大きく育っていっていただきたいと思います。本当におめでとうございました。
-

太田 弦 氏へ「贈賞にあたり」
選考委員 柴田 克彦(音楽評論家)/ 沼尻 竜典(指揮者)/ 吉田 純子(朝日新聞 編集委員)【贈賞の言葉】
太田弦さんの指揮を語るとき、多くの人が「正攻法」という言葉を使います。
選考会では、「楽曲のツボを押さえつつ、音楽に生気をもたらす力に秀でている」「どんなにクセの強いソリストでも、その個性を自然に引き立ててみせる」という評価の声があがりました。確かに「正攻法」という言葉がぴったりです。惜しくも今年1月に亡くなられた秋山和慶さんの指揮が、やはり「正攻法」という言葉でよく語られてきたことを思い起こします。
作曲家がこの一音に、このフレーズに、どんな思いをこめたのか。指揮者の仕事は、永遠の自問だと秋山さんは述べました。その理想の行き着く先は、『ところで、きょう指揮したのは?』というご本人の著書のタイトルに刻印されています。良き演奏に対する賛辞は指揮者ではなく、作曲家と、音像を生み出したオーケストラの奏者たちに贈られるべきである、と。公演後、コンサートホールを後にしながら、「きょうの演奏会は本当によかったねえ。あれ、ところで指揮していたのって誰だっけ?」。聴衆のそんな語らいの情景をつくることが、秋山さんが目指した境地でした。太田弦さんは、秋山さんと同質の志と理想を持つ指揮者だと思います。奇しくも秋山さんの旅立ちの年の受賞となったことは、精神の継承と未来の開拓を希求する現代のクラシック界において、少なからぬ重要な意味を持つものだと考えます。
昨年、九州交響楽団の首席指揮者に就任し、一家の主となりました。11月に開かれた定期公演のプログラムは、プッチーニの「4声のミサ曲」、小出稚子の「博多ラプソディ」(九響委嘱作)、そして石井眞木の「日本太鼓群とオーケストラのための『モノプリズム』」。攻めるにもほどがあると言いたくなるくらい意表を突く組み合わせでしたが、太田さんは全く肩肘張ることなく、ごくごく自然な風情で一夜の祝祭を寿ぎました。「モノプリズム」では、演奏の最中に思いがけなく「うぉー」という聴衆のおたけびが。1976年、ほぼ半世紀前に小澤征爾とボストン交響楽団、そして鬼太鼓座がタングルウッドで初演した時の興奮を追体験するようでした。淡々と、しかし確実に、博多っ子の祭りの心に火を付ける。これぞ「正攻法」の真骨頂です。
冒頭のトークの加減も絶妙でした。指揮者によるプレトークは、時として内輪受けに陥ったり、逆にサービス過剰になってしまったりして、なかなか難しいものですが、舞台に登場した瞬間からほっこりした笑顔と柔らかな口調で会場の空気をときほぐし、わかりやすい言葉で語りかけ、過不足なく楽曲への期待を誘いました。
「正攻法」で人を引き付けるために最も大切なのは、「塩梅」を知るということです。この若さでそれができる指揮者は、世界にもそうたくさんはいないと思います。
「こう聴かせよう」「盛り上げよう」という野心は、時として邪心と表裏一体になりがちです。楽曲の構造、および作曲家の意図を、虚心にわがものとする。そうして己が完全に媒介となってはじめて、演奏に自身の「色」がにじみ出る。そういう本質を、太田さんはすでに得心しています。それは、自身の演奏が何らかの批判を受けた時に、「私の個性である」と言い訳をしない、という覚悟に通じます。
どんなレパートリーも、水準以上に外れなくこなす。そういう能力を「当たり前」とし、軽視すべきではありません。日本のオーケストラを安定的に支え、新たな才能を受け入れ、輝かせてゆく。そうしたプロセスのなかで、大輪の花がゆっくりと開いてゆく瞬間を、わくわくしながら見守っていきたい。太田弦さんこそ、心からそう思わせてくれる存在です。【贈賞式でのスピーチ】(吉田純子選考委員)太田弦さん、おめでとうございます。前回の受賞者である杉山洋一さんより20歳以上若く、非常にフレッシュなのですが、それでいて、すでに不思議な安定感をお持ちの方でもあります。代役として立たれても、「ああ、今日は太田弦さんか」と安心できるのです。
昨年からは、九州交響楽団の首席指揮者を務めておられます。31歳にして、一国の主となりました。長きにわたり首席指揮者、音楽監督として同楽団に君臨されてきた大ベテランの小泉和裕さんから、誰が新しいバトンを受け取るのか。私は2017年から1年間、福岡に赴任していたのですが、その頃から楽団は真剣に次のシェフを探していました。太田弦さんに決まったと聞いたとき、当時の音楽主幹の深澤功さんに「いやー良かったですね、ほんとうに良い人を選びましたね」って思わず言ってしまって。深澤さんも「そうでしょう、そうでしょう、本当に良いでしょう!」と嬉しそうでした。
でも、そのあとふと気付いたのですが、私、それまで太田さんの演奏自体をあまり聴いたことがなかったんです。なのに、なぜ、こんなに太田さんが凄いって思っているんだろう……と。それを確かめたくて2024年11月、太田さんが指揮する定期演奏会を聴きに博多に参りました。その時のプログラムがプッチーニの「4声のミサ曲」、小出稚子さんの「博多ラプソディ」、そして石井眞木さんの「モノプリズム」。率直に申しまして、かなりとっ散らかったプログラムですよね(笑)。これをどうまとめてみせるのか、お手並み拝見といった気持ちで出かけたのですが、まず、太田さんのプレトークが良かったんです。指揮者の人たちは、基本的にみんなおしゃべりが上手なんですが、ちょっと思いが強すぎて話しすぎちゃったり……ということもあったりします。
でも、太田さんのお話はわかりやすいだけではなく、いろんな加減がちょうど良く、お客さんがどんどんニコニコ顔になってゆくのがわかるんです。ウケを取るとか、そういうことは全く考えておられない風情なのに、おのずと空気がやわらかくなっていく感じがある。驚いたのは、最後の「モノプリズム」の途中で、お客さまから歓声が出たことです。お客さまが演奏中に感極まって大声を出すというのは、普通のオーケストラ公演ではあまり考えられないことです。それだけ太田さんが、お客さんが能動的に反応できる空気を作ったということなのだと思いました。お客さんにサクラがいたんじゃないかとも思ったのですが(笑)、誰に話を聞いても、誰かが事前に仕込んだ形跡はありませんでした。
私が何となく太田さんに抱いていた安心感というものは、こういうことなんだと腑に落ちました。もちろん、太田さんの指揮の技術の素晴らしさがすべての前提としてあるのですが、周囲の人たちを安心させ、奏者たちのモチベーションを上げながら音楽を作っていくことが本能的にできる、いまの音楽界にとても必要な人だという感を新たにいたしました。
この1年ほどの間、小澤征爾さんと秋山和慶さんが相次いで亡くなられました。お二人ともご周知の通り、齋藤秀雄先生のとても大切なお弟子さんなのですが、指揮は非常に対照的です。小澤さんは、情念の火花を散らしながら誰しもを虜にしていく。秋山さんは、なるべく自分は前に出ず、作曲家の魂や精神性を浮き彫りにしてゆく。秋山さんが目指した境地は、彼の著書のタイトルに示されているとおり、「ところできょう、指揮したのは?」。指揮者の存在を全く感じさせぬまま、お客さまたちに作曲家との幸せな出会いの体験をしてもらうということが、秋山さんの理想でした。
それと同じとまで言うことはできないでしょうが、私は太田さんにも近い精神を感じます。何かを誇るとか、奇を衒うとか、そういうのではなく、作品の精神の核をつかみ、それを受け入れる場の空気をつくりながら、自然にお客さまに届けてゆく。小澤さんと秋山さんがいなくなって、いま、多くの人が心にぽっかり穴が空いたように感じていると思います。そういう時期に、太田さんのような若手が出てきてくださったことをとても頼もしく感じておりますし、齋藤秀雄メモリアル基金賞に選出することができたということを、選考委員のひとりして心より誇りに思います。
まったくの余談ですが、太田弦さんって良い名前ですよね。(チェロ部門の受賞者の)北村陽さんも。ヨウさん、ゲンさんって、外国に行っても親しみを持って呼ばれそうな気がします。太陽のように人々を照らす陽さんと、世界の調和を導いてくださる弦さん。良い名前の人には良い気が宿るものだなあと、つい思いついて言ってしまいました、失礼しました。太田さんのますますのご活躍をお祈りするとともに、みなさまにはぜひ博多の地で、太田さんと九州交響楽団の響きに耳を傾けていただけたらと思います。
受賞の言葉
-

北村 陽(チェロ)
【受賞の言葉】
この度は「齋藤秀雄メモリアル基金賞」をいただき、大変光栄に思うとともに、身の引き締まる思いです。ソニー音楽財団の皆様、大変お世話になった先生方、いつも温かく見守り支えてくださる方々に心より感謝申し上げます。私は高校より、齋藤秀雄先生ゆかりの桐朋学園に在籍し、今は齋藤先生も学ばれたベルリン芸術大学に留学しています。
私が師事するイェンス=ペーター・マインツ先生のレッスン室には、齋藤先生の師であるチェリスト、エマヌエル・フォイアマンの等身大を超える巨大なポートレートが飾られています。マインツ先生はフォイアマンについて、技術や音楽解釈は100年後の今でも通用するもので、室内楽もそれまででは考えられないような次元の音楽を奏でた音楽家であると仰っています。フォイアマンを前にレッスンを受けながら、ベルリンでヨーロッパの文化や歴史、音楽を最大限に吸収した齋藤先生が海を越え、その教えを日本に伝え、時代を超えて私もそれらを学びこの地にいると思うと、深い繋がりを感じます。私はチェロという楽器に心惹かれてからというもの、本当に多くの素晴らしい先生方との出会いがありました。
齋藤先生に師事された山崎伸子先生には9年間お世話になり、さまざまな音の出し方を徹底的にご指導いただきました。レッスン中に聴かせてくださった山崎先生の多彩な音色は、私の心の中に多く残されています。それらは演奏のイメージを広げる源であり、私の音楽の礎となっています。齋藤先生に師事され、私が高校からご指導いただいている堤剛先生は、グローバルな視点からアドバイスをくださいます。レッスンでいただいた言葉ひとつひとつは、ベルリンに来てからも、実はこういう意味だったのかと新たに気付くことが沢山あります。
そして、堤先生が私に大きな力を与えてくださった言葉があります。
「誰かがやっているから、誰もやっていないからではなく、自分を信じてやりなさい。」
その言葉をいただいた時に、私はそれまで内に秘めていたものが一気に噴き出すような、心が喜びに満たされていく感覚がありました。
ベルリンで師事するマインツ先生は、深い楽譜の読み方を通して私ならではの表現ができるよう、多くのアイデアやヒントを与えてくださいます。また、私はあらゆる面で多くの方々に支えられ、最高の環境で学び続けられることに感謝してもしきれません。私は世界中の人々が音楽で繋がり、音楽によって心穏やかな平和な日々を送ることができるようになることを心から望んでいます。
齋藤先生が残されたものを受け継ぎ、これからも学び続けていきたいと思います。人々に寄り添い、ともに分かち合える音楽家になれるよう精進いたします。【贈賞式でのスピーチ】
この度は「齋藤秀雄メモリアル基金賞」をいただき、大変光栄で身の引き締まる思いです。ソニー音楽財団の皆様、大変お世話になった先生方、いつも温かく支えてくださる方々に心より感謝申し上げます。私は高校より、齋藤秀雄先生ゆかりの桐朋学園に在籍し、今は齋藤先生も学ばれたベルリン芸術大学に留学しています。私が師事するイェンス=ペーター・マインツ先生のレッスン室には、齋藤先生の師であるチェリスト、エマヌエル・フォイアマンの等身大の巨大なポートレートが飾られています。マインツ先生は、フォイアマンの技術や音楽解釈は100年後の今でも通用するもので、室内楽もそれまででは考えられないような次元の音楽を奏でた音楽家であると仰っています。
そのため、フォイアマンのソロはもちろん、室内楽の演奏をたくさん聴くように言われます。まさに、現在の桐朋でも室内楽がとても重要とされています。ベルリンでヨーロッパの文化や歴史、音楽を最大限に吸収した齋藤先生が、海を越え、その教えを日本に伝えられました。フォイアマンの写真を前にレッスンを受けながら、時代を超えて、私もそれらを学びこの地にいると思うと、深い繋がりを感じます。
私はこれまでとても恵まれた環境で学んできました。初めてチェロを習ったギア・ケオシヴィリ先生や太田真実先生から、音楽の喜びを知ることができ、山崎伸子先生によって表現の幅を広げ、多彩な音色を知り、堤剛先生には過去の偉大な音楽家の教えから、現代の解釈に至るまで、グローバルな視点でのアドバイスをいただいてきました。ベルリンのマインツ先生からは、深い楽譜の読み方を通して私ならではの表現ができるよう、多くのアイデアやヒントをいただいています。
また、私の育った兵庫県の西宮市には、兵庫県立芸術文化センターがあり、私は幼い頃からそこに何度も足を運びました。阪神・淡路大震災からの「心の復興のシンボル」として建てられた兵庫県立芸術文化センターでは、国内外で活躍するアーティストのコンサートが開かれていて、そういった生の演奏を間近で聴き、演奏会後のサイン会で、アーティストの皆様とお話しができたことは、私にとってかけがえのない経験となり、音楽家という存在がとても身近に感じるきっかけとなりました。そして、そのホールを拠点に活動している「佐渡裕とスーパー・キッズ・オーケストラ」というジュニアオーケストラに小学2年生で入団した時は、小学生から高校生までのメンバーやお客さまと「共に」音楽を作る喜びを知りました。東日本大震災の被災地を訪れた際は、人の営みがあったであろう場所に、家の土台しか残されておらず、自分たちの乗っているバスより高く積まれた瓦礫の中を移動し、演奏して回りました。私たちの演奏によって、「地震後泣くことすらできなかったけれど、初めて涙を流すことができました。ありがとう。」とおっしゃる方もおられて、音楽にできること、音楽の大切さを知りました。 今、ドイツのベルリンに留学して、ウクライナから来た学生や、兵役を終えてきた学生と共に学んでいます。街に多く存在するホロコーストの爪痕に囲まれて生活していく中で、戦争が遠い国の出来事ではないと日々実感しています。
私は、人が生きるためには音楽が必要であると信じています。そして、世界中の人々が音楽で繋がり、音楽によって、心穏やかに平和な日々を送れるよう望んでいます。人々の心に寄り添い分かち合える音楽家になれるよう、学び続けていきたいと思います。この度は、本当にありがとうございました。
-

太田 弦(指揮)
【受賞の言葉】
この度は名誉ある齋藤秀雄メモリアル基金賞を受賞させて頂くこととなり、大変光栄に思っております。
公益財団法人ソニー音楽財団の皆さま、選考委員の皆さま、先生、友人、今日まで教えを頂いてきた多くの皆さま、いつも支えて下さるマネージメント、そして家族に感謝しつつ、この素晴らしい賞をお受けしたいと思います。私の生まれる20年前に齋藤先生はお亡くなりになっていますので、当然私は直接教えを受けることは叶いませんでしたが、私の師である尾高忠明先生や高関健先生から、折に触れて様々な貴重なお話を伺うことが出来ました。
そのようにして触れさせて頂いた、齋藤先生の音楽や教育に対する姿勢や情熱に、深い尊敬の念を抱いております。思い返せば私が指揮を勉強したいと考えた12歳の頃、札幌では指揮を勉強出来る環境はありませんでした。そんな中で私が入手できた、数少ない指揮に関する本の一冊が齋藤先生の世界的名著「指揮法教程」でした。当時の私にとっては未知の世界へのパスポートのような存在で、誤字を発見するほど毎日のように読み込んでいました。
その結果、ほぼ独学で芸大の指揮科に入学する事が出来ましたので、直接お会いした事はなくとも、私も齋藤先生の教育への情熱に助けて頂いた1人だといえるのかもしれません。実際の演奏の現場においては、20代半ばの新人指揮者であった私にポストと多くの経験の機会を下さった大阪交響楽団、現在、充実した演奏活動を共にして下さっている仙台フィルハーモニー管弦楽団、そして大きな責任を持たせてくれた九州交響楽団を中心に、日本中のオーケストラに育てて頂きました。この場をお借りして感謝を申し上げます。
皆様ご存知のようにこの1〜2年の間だけでも多くの尊敬する大先輩指揮者がお亡くなりになってしまいました。誰もが日本の指揮界の先行きを案じるこのタイミングで、このような大きな賞を頂くことになり責任を感じております。
まだ31歳になったばかりの私に出来ることは多くはありませんが、変わらず真面目に真摯に音楽とオーケストラに向き合い、精進して参ります。これからもご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。この度は本当にありがとうございました。【贈賞式でのスピーチ】
皆さま、本日は足元の悪い中、お越しくださりありがとうございます。ご紹介にあずかりました太田です。改めまして、この度は、齋藤秀雄メモリアル基金賞という、非常に重要な賞を頂くこととなり、大変光栄に思っております。ソニー音楽財団の皆さま、選考委員の皆さま、ここまで育てて下さった尾高先生と高関先生をはじめに、多くの教えを与えて下さった皆さま、共に学んだ仲間たち、オーケストラの現場でいつもお世話になっている皆さま、指揮活動を支えて下さるマネージメント、そして家を空けがちなので、いつも迷惑をかけている家族に感謝しつつ、この素晴らしい賞をお受けしたいと思います。
まず、私と齋藤先生の関わりについてお話させて下さい。
最初に、私が齋藤先生のお名前をしっかりと認識したのは、恐らく12歳頃、指揮者になりたいと考え、図書館などで音楽関係の本をとにかく片っ端から読み漁っていた頃だと思います。そこで先生の音楽教育への情熱と、指揮法教程という、先生の書かれた指揮の教科書があることを知り、お年玉の残りを握りしめて楽譜屋さんに買いに向かったこと、そして何故か妙に緊張して、冷や汗をかきながらレジへと持って行ったことを今でもよく覚えています。
当時、というより恐らく今もでしょうが、私の故郷の札幌では、指揮を勉強出来る環境は全くと言って良いほどありませんでした。そういう状況でしたので、独学で勉強するしかない私にとっては、齋藤先生の書かれたことが指揮者への数少ないみちしるべであり、頼りになる存在でした。毎日のように読み込んで、少しでも書いてあることを理解しようと努力していたことを思い出します。
その甲斐あってか、運良く芸大の指揮科に入ることが出来、そこで尾高先生と高関先生の素晴らしい指導を受けることが出来ました。お二人とも齋藤先生との関わりが深いので、色々なお話を聞けたのが、今でも大きな財産です。これは想像が入りますが、あれだけお忙しい先生方が、学校で教えることに時間を割いて下さっていたのは、齋藤先生の教育への想いを繋ごうとお考えだったからなのかもしれません。もしそうだとすると、ここでも齋藤先生に間接的に僕は助けて頂いたことになります。
そして大学4年の時の東京国際音楽コンクール(今は指揮者コンクールですね)で2位を頂き、今に至る指揮活動が始まるのですが、このコンクールも齋藤先生が創設時に深く関わり、初代審査委員長を務めていらっしゃいます。このように思い返すと、自分でも驚くほど多くの節目節目に齋藤先生の影響があり、この賞を頂くことに改めて背筋が伸びる思いです。
もちろん、実際の演奏の現場においては、日本中のオーケストラに育てて頂きました。特に20代半ばであった私に、ポストと多くの演奏の機会を下さった大阪交響楽団、現在、充実した演奏活動を共にして下さっている仙台フィルハーモニー管弦楽団、そして首席指揮者という大きな責任を持たせてくれた九州交響楽団には、特に大きな感謝の念を持っています。この場をお借りして感謝を申し上げます。
皆様ご存知のようにこの1〜2年の間だけでも多くの尊敬する大先輩指揮者がお亡くなりになってしまいました。誰もが日本の指揮界の先行きを案じるこのタイミングで、このような大きな賞を頂くことになり責任を感じております。
まだ31歳になったばかりの私に出来ることは決して多くはありませんが、変わらず真面目に真摯に音楽とオーケストラに向き合い、精進して参ります。これからもご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。この度は本当にありがとうございました。
プロフィール
-

北村 陽(チェロ)
2004年生まれ。9歳でオーケストラと初共演し、翌年初リサイタルを行う。2017年 第10回若い音楽家のためのチャイコフスキー国際コンクールに満場一致で優勝。2022年 第18回ハチャトゥリャン国際コンクール第2位。2023年 第29回ヨハネス・ブラームス国際コンクール第1位。第92回 日本音楽コンクール第1位を受賞し、全部門を通じて最も印象的な奏者に贈られる増沢賞、岩谷賞(聴衆賞)、黒柳賞、徳永賞、INPEX賞を受賞。2024年9月 ジョルジュ・エネスク国際コンクールのチェロ部門で日本人として初優勝。同年11月パブロ・カザルス国際賞第1位を受賞と、次々に快挙を成し遂げて注目をあびる。
これまでに小林研一郎、高関健、大友直人、藤岡幸夫、山田和樹、アンドレイ・フェーヘル各氏の指揮により、多数の楽団と共演。2020年ユリアン・シュテッケルの代役で井上道義指揮、読売日本交響楽団と共演し好評を博す。
2021年霧島国際音楽祭賞受賞。遠山基金、宗次エンジェル基金/日本演奏連盟、ヤマハ音楽振興会、ジェスク音楽振興会、江崎スカラシップより奨学金を授与され、第52回江副記念リクルート財団奨学生、2023、24年度ローム ミュージック ファンデーション奨学生。
現在、桐朋学園大学ソリスト・ディプロマ・コースにて堤剛、ベルリン芸術大学にてイェンス=ペーター・マインツ各氏に師事。これまでに山崎伸子、室内楽を磯村和英各氏に師事。 2025年第26回ホテルオークラ音楽賞を受賞。
使用楽器は上野製薬株式会社より貸与された1668年製カッシーニ。 -
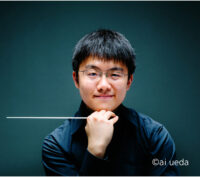
太田 弦(指揮)
1994年北海道札幌市に生まれる。幼少の頃より、チェロ、ピアノを学ぶ。
東京藝術大学音楽学部指揮科を首席で卒業。学内にて安宅賞、同声会賞、若杉弘メモリアル基金賞を受賞。同大学院音楽研究科指揮専攻修士課程を修了。
2015年、第17回東京国際音楽コンクール〈指揮〉で2位ならびに聴衆賞を受賞。第30回(2022年度)渡邉曉雄音楽基金音楽賞受賞。指揮を尾高忠明、高関健の両氏、作曲を二橋潤一氏に師事。山田和樹、パーヴォ・ヤルヴィなどの各氏のレッスンを受講する。これまでに読売日本交響楽団、東京交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団、札幌交響楽団、群馬交響楽団、名古屋フィルハーモニー交響楽団、大阪フィルハーモニー交響楽団、大阪交響楽団などを指揮、今後さらなる活躍が期待される若手指揮者筆頭。2019年4月から2022年3月まで大阪交響楽団正指揮者を務める。2023年4月より仙台フィルハーモニー管弦楽団指揮者、2024年4月より九州交響楽団首席指揮者に就任。
2021年2月、オクタヴィア・レコードよりシューベルト:交響曲第8(9)番「ザ・グレイト」(新日本フィルハーモニー交響楽団公演ライブ収録)をリリース。新型コロナウイルスによる緊急事態宣言明けに行われた公演の緊張感の中、太田のエネルギー溢れる「ザ・グレイト」が聴衆の話題をさらった。
2024年7月には、同年4月に九州交響楽団首席指揮者就任記念コンサートとして開催した第420回定期演奏会のライブ録音のCDがオクタヴィア・レコードより発売、好評を博している。